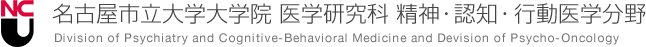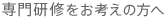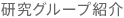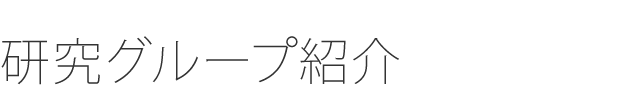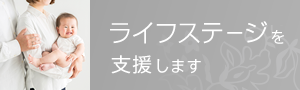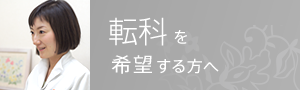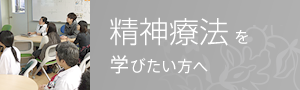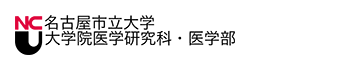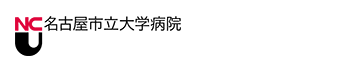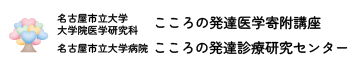HOME > 研究グループ紹介 > 研究グループ紹介> 研究グループ紹介
児童精神医学研究会
児童研究会では月1回(主に第2火曜日)は、インシデント・プロセス法による症例検討会を行っています。実際の臨床現場で困った一場面を取り上げ、自分だったら、または他の人だったら、どんな対応をするのか、検討していく形で行います。一般論や理論的には分かっているけれども実際の場面ではうまく対応できない、しっかり話を聞きなさいと教えられるけれどどうやって聞けばいいのか全く思いつかない、自分の方法以外にもっとよく対応できる方法があるというのなら聞いてみたい、などなどの事例に対してなるほどと腑に落ちるような対応方法が見つかります。
また児童の症例については、主に外来での新患紹介を行い、診断の見立てと今後の治療の方向性を決定します。難しい症例などは新患時のみに限らず、その後の経過についても検討していきます。実際に対応している患者で困っている際は、いつでも検討を行いますのでご相談下さい。また月1回程度、児童にあまり馴染みのない方向けに、クルズスのようなことを行っていく予定です。子どもの診方、広汎性発達障害の診方、ADHDの診方などです。また、物足りない方には、それぞれに新しいトピックを出してもらい、話題を共有していきたいと考えています。
精神療法研究会(精神療法グループ)
精神疾患に対する治療法は、大きく分けて薬物療法と精神療法の2つがあります。精神療法には様々なものがありますが、私たちは認知行動療法(CBT)や対人関係療法(IPT)、アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)、EMDR(眼球運動による脱感作と再処理法)などの治療法に取り組んでおります。そして、精神療法の臨床・教育・研究の3方面を結びつけながら皆で高めあっていく場として、研究会を開催しています。
臨床・研究
私たちは今まで「本当に患者さんの役に立つ治療とは何か」を意識して、精神療法の臨床研究を行ってきました。海外の研究者とも積極的に交流し、多くの英語原著論文を発表しています。
2023年4月現在、次の研究を実施・計画しています。
アクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)
- 慢性疼痛のACT
- 慢性耳鳴のACT
- 臨床実習中の医学生のバーンアウト改善・予防目的のグループACT
- 臨床実習中の医学生のバーンアウトについてのコホート研究
- 臨床実習中の医学生のバーンアウト尺度日本語版の妥当性/信頼性研究
- 初期研修医の発達特性とバーンアウトについての横断研究
対人関係療法(IPT)
- 遺族のうつ病・遷延性悲嘆症・PTSDに対するオンラインIPT
社会と地域のメンタルヘルス
-
家族:入院患者さんのご家族を対象に家族療法を毎週金曜日の午後に実践しています。家族療法のエビデンスが示されている統合失調症や神経性やせ症はもとより、他の精神疾患に対しても家族療法を臨床的に応用しています。
学校:名古屋市立大学保健管理センターにおいて、心理スタッフと協力しながら学生を対象にカウンセリングを行っています。相談者のニーズに合わせた統合的なアプローチの他、カウンセラーの専門性に応じて認知行動療法を代表とする特異的なアプローチも行えます。
職場:名古屋市役所の産業医として臨床活動を行っています。保健管理センターの体制が整い次第、大学と病院職員にもメンタル不調の予防や介入を提供していきます。研究活動の詳細は、次のページをご覧ください。研究活動
教育・普及
外部の講習会などにも積極的に参加して、精神療法の治療技術だけでなく教育技術も取り入れています。これらの経験を生かし、後期研修医(レジンデント)や大学院生を対象に、講義や見学だけではなくスーパービジョン(同席による指導)を行っています。このように実践的で質の高い教育を行うことで、良い治療者を育て、より良い治療を提供できるように努力しています。
医学教育分野では、医学生のメンタルヘルス向上、メンタルヘルス・リテラシー向上を目標にアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)の要素を取り入れた講義やプログラムを実施しています。
こちらも参照ください。メンタルヘルスと心理的柔軟性~怒りや恥などの感情に対処する新たな視点~
社会と地域のメンタルヘルス分野では、家族療法のセッションに参加、さらに実践することにより実地でスキルを習得できます。毎回のセッション後、指導医がスキルの解説を含めて振り返りをするので理解が深まり、自分の診療に取り入れていけます。
また、当院退院後の神経性やせ症の患者さんをサポートするご家族を対象に家族会を毎月第4金曜日の夕方に開催しています。その家族会に参加することによりグループ介入のスキルを習得できます。
研究
私たち名古屋市立大学精神療法研究会(精神療法グループ)は、これまでの臨床・教育の蓄積を活かして、精神疾患および身体疾患の患者さんに貢献できる医療者の育成に力を入れています。
このように臨床・教育・研究の3方面すべてを結びつけながら皆で高めあっていく場として、今は不定期となっていますが、研究会を開催しています。精神療法に興味のある方、私たちと一緒に学びませんか。

精神療法研究会(精神療法グループ)
CL・サイコオンコロジー・緩和ケア研究会
当グループでは、がん医療におけるこころの問題を扱う領域であるサイコオンコロジーを中心に、緩和ケア、コンサルテーション・リエゾン精神医学なども含めた幅広い領域の臨床、研究、教育を行っています。
臨床
がんやその他の身体疾患のために入院中の患者に関する精神科コンサルテーションに対して、専門チームを結成して対応を行っており、年間約600名の入院患者にサービスを提供しています。また緩和ケア医、看護師、薬剤師、臨床心理士とともに緩和ケアチームを結成し、約400件の入院患者の診療依頼を受けています。
研究
がん患者のQOL向上に資するような研究を行っています。また国内有数のサイコオンコロジーおよび緩和ケアの研究グループと共同研究も行っており、これらの成果として、毎年10本程度の英文原著論文を発表しています。
教育
医学部学生、卒後研修、レジデント、大学院生など、それぞれの段階に応じて必要な教育を提供できるよう配慮しています。
- 当院精神科レジデンシーにおいては、レジデント2年目で個々の希望に応じて3-6ヶ月間、CL・サイコオンコロジー・緩和ケアチーム専従となって臨床研修を行うことで、総合病院に赴任した際に求められる臨床知識・技能を習得することができます。
- 将来この領域の専門を目指すことをお考えでしたら、更に大学院に進んで臨床・研究を学ぶことも可能です。
私たちとともに学ぶ医員、大学院生を募集しています。また数週間から数カ月間の短期研修などについてもご要望に応じて対応させて頂きます。
詳しくは、サイコオンコロジーグループ
老年精神医学・高次脳機能・神経心理グループ
認知症性疾患を中心に、脳画像や神経心理学的アプローチによるメカニズムに関する研究や臨床上対処に苦慮することが多い精神行動障害(BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia )の評価法開発や病態解明研究、患者さんご家族のQOL向上に資する非薬物学的介入法の開発などに取り組んでいます。中でも、神経心理学を用いたアプローチは、名市大が伝統的に得意としてきた分野であり、現在も臨床心理士や言語聴覚士の協力を得ながら積極的に取り入れています。
最近では、認知症患者さんの焦燥感の評価法を開発し(Reliability and validity of the Japanese version of the Agitated Behaviour in Dementia Scale in Alzheimer’s disease: three dimensions of agitated behaviour in dementia. Torii K, et al, Psychogeriatrics 2011)、本評価法を用いてその神経基盤に迫る研究を行っています(Neural basis of three dimensions of agitated behaviors in patients with Alzheimer disease. Banno K, et al. Neuropsychiatr Dis Treat 2014)。
臨床と脳波研究会
臨床脳波研究会では、現在、John Hughlings Jacksonの論文の抄読と症例検討を行っています。症例検討はてんかん、精神疾患の脳波所見を検討しながら、症例について考察します。関連病院の先生方で検討したい症例がありましたらお気軽に東までご連絡ください。
脳画像研究グループ
脳画像研究グループでは精神疾患の病態や治療効果の神経基盤に関する研究に取り組んでいます。
精神科領域の脳画像研究は現在とてもホットな領域です。これまで電気痙攣療法(ECT)の患者さん、社交不安症の患者さんなどに協力いただき、国立がん研究センター、広島大学、生理学研究所、包括脳などから研究手法の指導を受け、構造画像のマニュアルトレーシングや全脳解析(Voxel based morphometry: VBM)、社交不安症の自己に対する恥ずかしさ情動に関連した機能的MRI(fMRI)研究などを行ってきました。当院では、中央放射線部の協力によりfMRIができる環境が整い、種々の画像解析ソフトも揃っています。
臨床精神神経薬理グループ
臨床精神神経薬理グループでは,精神神経疾患の薬物治療に関する、臨床現場で真に役立つエビデンスを創出することを目的とした研究を行っています。インパクトの大きな研究としては、客員教授の古川教授が中心メンバーとして実施された新規抗うつ薬の有用性および忍容性を明らかにしたメタアナリシス1などがあります。
また効果と忍容性のバランスに優れたSSRIと、効果は高いものの忍容性がその効果ほどではないNaSSAを、どのように組み合わせると最も治療効果が期待できるのかを解明するための実践的で大規模な無作為化比較試験2, 3(研究のホームページ:http://ebmh.med.kyoto-u.ac.jp/sund/)にに、明智が共同主任研究者として参加しました。本研究は2015年3月で2000名を超える患者さんのエントリーを終え、うつ病の薬物療法としては、世界で3本の指に入る規模の臨床試験となりました。2015年10月にフォローアップを終え、2018年に結果が論文化されました4。私たちの普段の臨床を変える知見が得られています!その他、この臨床試験のデータを用いてさまざまな追加解析を行い、その結果を論文化しています5-8。
- 1.Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G, Chaimani A, Atkinson LZ, Ogawa Y, Leucht S, Ruhe HG, Turner EH, Higgins JPT, Egger M, Takeshima N, Hayasaka Y, Imai H, Shinohara K, Tajika A, Ioannidis JPA, Geddes JR. Lancet. 2018 Apr 7;391(10128):1357-1366.
- 2.Furukawa TA, Akechi T, Shimodera S, Yamada M, Miki K, Watanabe N, Inagaki M, Yonemoto N. Strategic use of new generation antidepressants for depression: SUN(^_^)D study protocol. Trials. 2011 May 11;12:116.
- 3.Shimodera S, Kato T, Sato H, Miki K, Shinagawa Y, Kondo M, Fujita H, Morokuma I, Ikeda Y, Akechi T, Watanabe N, Yamada M, Inagaki M, Yonemoto N, Furukawa TA; SUN(^_^)D Investigators. The first 100 patients in the SUN(^_^)D trial (strategic use of new generation antidepressants for depression): examination of feasibility and adherence during the pilot phase. Trials. 2012 Jun 8;13:80.
- 4.Kato T, Furukawa TA, Mantani A, Kurata K, Kubouchi H, Hirota S, Sato H, Sugishita K, Chino B, Itoh K, Ikeda Y, Shinagawa Y, Kondo M, Okamoto Y, Fujita H, Suga M, Yasumoto S, Tsujino N, Inoue T, Fujise N, Akechi T, Yamada M, Shimodera S, Watanabe N, Inagaki M, Miki K, Ogawa Y, Takeshima N, Hayasaka Y, Tajika A, Shinohara K, Yonemoto N, Tanaka S, Zhou Q, Guyatt GH; SUN☺D Investigators. Optimising first- and second-line treatment strategies for untreated major depressive disorder - the SUN☺D study: a pragmatic, multi-centre, assessor-blinded randomised controlled trial. BMC Med. 2018 Jul 11;16(1):103.
- 5.Akechi T, Kato T, Watanabe N, Tanaka S, Furukawa TA; SUN☺D Investigators. Predictors of hypomanic and/or manic switch among patients initially diagnosed with unipolar major depression during acute-phase antidepressants treatment. Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Feb;73(2):90-91.
- 6.Akechi T, Kato T, Fujise N, Yonemoto N, Tajika A, Furukawa TA; SUN☺D Investigators. Why some depressive patients perform suicidal acts and others do not. Psychiatry Clin Neurosci. 2019 Oct;73(10):660-661
- 7.Akechi T, Mantani A, Kurata K, Hirota S, Shimodera S, Yamada M, Inagaki M, Watanabe N, Kato T, Furukawa TA; SUND Investigators. Predicting relapse in major depression after successful initial pharmacological treatment. J Affect Disord. 2019 May 1;250:108-113.
- 8.Akechi T, Sugishita K, Chino B, Itoh K, Ikeda Y, Shimodera S, Yonemoto N, Miki K, Ogawa Y, Takeshima N, Kato T, Furukawa TA. Whose depression deteriorates during acute phase antidepressant treatment? J Affect Disord. 2020 Jan 1;260:342-348.
研究活動(社会・地域精神医学グループ)
未来の地域のメンタルヘルスを向上させるため、エビデンスが示されている標準的な介入に留まらない私たちのアイデアを科学的な枠組みで実証する臨床研究を進めています。
現在、以下の研究に取り組んでいます。
<家族療法研究>
- 重度精神障害者の介護に関連した家族のポジティブおよびネガティブ感情を、介護過程の曼荼羅的理解のもと、評価する新たな尺度を作成し、その信頼性と妥当性を検証しています。
- 並行して、介護の肯定的側面を高め患者のリカバリーを促進に波及する新たな家族療法を開発しています。
- 研究課題の詳細は、次の科研費のサイトをご覧ください
➡https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K14420/
<学生のメンタルヘルス研究>
- 京都大学 健康増進・行動学分野と共同し、スマートフォン認知行動療法(CBT)を用いて大学生へのうつ病予防効果と最適なCBTの介入要素の組み合わせを検証しています。
- 研究結果をもとに最新の情報技術を用いた大学生へのメンタルヘルス介入の普及を目指していきます。
- 研究内容の詳細は、次の京都大学のサイトをご覧ください
➡https://www.hoken.kyoto-u.ac.jp/hct/
<職場のメンタルヘルス研究>
- 今後、名古屋市立大学 公衆衛生学分野と共同して研究を行っていく予定です。
過去、以下の演題を学会発表しました。
- 1. ブレクスピプラゾールが奏功したパーキンソン精神病の一症例
浅沼 恵美, 真川 明将, 白石 直, 外ノ池 文乃,明智 龍男, 木村 和哲
第29回日本医療薬学会年会 2019年11月 - 2. 父子関係への家族介入後、急激なうつ病の改善と宗教観の変化を示したキリスト教牧師の一例
小川 晴香, 白石 直, 沢田 光代, 石川 貴康, 真川 明将, 関口 文乃, 明智 龍男
第115回日本精神神経学会学術総会 2019年6月 - 3. 神経性無食欲症に対する入院行動制限療法において、家族介入による増強効果が示唆された1例
小川 晴香, 白石 直, 山田 敦朗, 明智 龍男
第177回東海精神神経学会 2019年1月
これら研究と臨床、教育を三位一体として、現代と未来の社会において人々のメンタルヘルスの向上に貢献できるプロフェッショナルを目指す私たちと共に活動しませんか。
ご希望の方は、当教室の見学に来ていただいた際、
社会・地域精神医学グループの代表者(https://researchmap.jp/nao-shiraishi/)
またはメンバーから当グループの活動について直接お話させていただきますので、その旨、お問い合わせのメールにご記載ください。
- 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野
- 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 Phone: 052-851-5511(代表) Fax: 052-852-0837
Copyright © Dept of Psychiatry, Nagoya City Univ Graduate School of Medical Sciences, All Rights Reserved.