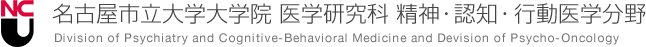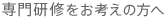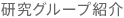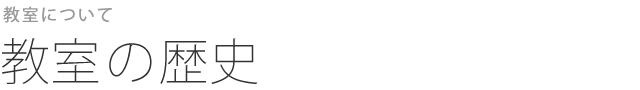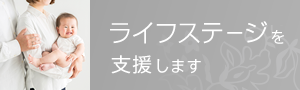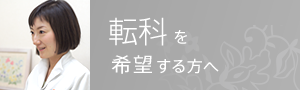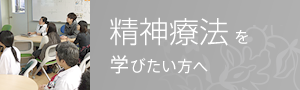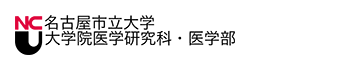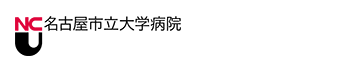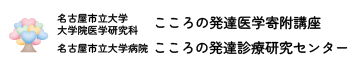初代 児玉 昌教授 (1943-1951)
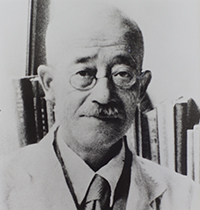
名古屋市立大学医学部の前身の名古屋市立女子高等医学専門学校において、児玉 昌教授が「精神科学」の講義を担当し、付属医院での精神科の診療を始められたのは1943年(昭和18年)のことであった。場所は今の名古屋市博物館のところであったと聞いている。
児玉教授は独逸語協会中学校のご出身で、第一高等学校へ進まれ、東京帝国大学医科大学を1917年(大正6年)に卒業され、精神病学教室の呉秀三教授*に師事し、東京府立松沢病院の医長を長く勤められた。併せて、小金井治療教育所を創設し精神薄弱の治療教育をされ、この方面での日本における創設者であったという。
1931年(昭和6年)に愛知県立精神病院**の初代院長として赴任され1943年まで勤められた後、名古屋市立女子高等医学専門学校に赴任された。
戦後の医学教育改革に伴い、1947年に女子医専が名古屋女子医科大学に改組され、1950年に現在の名古屋市立大学医学部となったのも、児玉教授の頃ということになる。
1951年に名市大を退官後は千葉に戻られ、「我が庭の吉野櫻の花吹雪、ちりしく中に死なんとぞおもふ」という歌を賦して1953年に逝去された。
*わが国における精神医学と精神医療の建設者ともいうべき精神医学者。「精神病者私宅監置ノ実況及ビ其統計的観察」(1918年)のなかで述べた「わが国十何万の精神病者はこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ぬるものというべし」という言葉は有名である
**現、愛知県立城山病院
2代 村上 仁教授 (1951-1955)
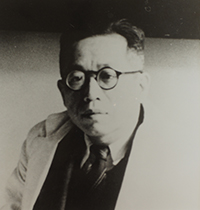
精神病理学の京都学派の泰斗、村上 仁教授が、名古屋市立大学の初代学長戸谷銀二郎先生に請われて名市大に赴任されたのは1951年であった。翌1952年には名著『異常心理学』(岩波書店)を出版され、ここに名市大精神科のバックボーンの一つである精神病理学研究の礎が築かれた。『異常心理学増補改訂版』の扉には「異常心理学は心理学と精神医学の境界領域にあって(中略)、本書は異常心理学の諸潮流から、精神病理の機構と病像を個体の環境に対する適応異常という観点に立って説明するアメリカの諸学説、および病変の器質的・内因的要因を構造論的、現象学的に把握するヨーロッパの諸理論を析出し、両者の統合的理解を意図して概説したものである」と解説されている。
村上教授は岐阜のご出身で、京都帝国大学医学部を1933年(昭和8年)に卒業され、上記戸谷学長とご父君同士が京大の同期生であったというご縁であった。村上教授については、教室内で代々語り継がれている逸話は多いが、戸谷学長から「精神科では器具などは必要ないだろうから、書籍は自由に買ってよい」と言われて、図書や雑誌はかなり手広く購入されていたという話はよく聞く。
現在の同門会名簿の歴代入局者名簿に大先輩のお名前を拝見するのも、村上教授の時代からである。1952年(昭和27年)入局の矢野先生のご寄稿によると「治療も28年頃には向精神薬はまだ登場せず、電気ショック療法、インスリン療法、持続睡眠療法くらいで、内服はブロームカリという水薬やブロバリン、フェノバルビタールを処方していました。それでも病棟看護にひどく困ったというようなことは聞きませんでした。時には進行麻痺で躁状態の和尚さんが和服の尻をからげて特別病棟の床掃除を始め、そこの婦長さんに怒られて連れ戻しに行ったり、破瓜病の患者さんが突然ボイラー室の高い煙突に上ってしまい皆がその下に集まって口々に呼んでも知らん顔して手放しで周囲を眺め回し、今にも落ちるんではないかと冷や汗ものでした。30分くらいでまたするすると下りてきて何事もなかったように病室に戻り、理由も判らずじまいでした。それでも、大きな問題になるような事故もなく過ごせたのは、村上教授の開放的な治療方針や医局が病棟内にあって患者さんとのコミュニケーションも良かったこと、看護婦さんも特に身構えることなく患者さんと普通に接していたことなども大きな要因だったと思います」と回顧されている。
村上教授は1955年京都大学教授に転出され、その後も『精神病理学論集』(みすず書房、1971)。訳書 ヴィオー『知能』(1951)フィルー『精神力とは何か』(1952)(以上、白水社)ミンコフス キー『精神分裂病』(1954)ボス『性的倒錯』(共訳、1957)『分裂病の少女の手記(改訂)』(共訳、1971)ウェルダー『フロイト入 門』(1975)ラプランシュ/ポンタリス『精神分析用語辞典』(1977)(以上、みすず書房)ほかを上梓されて、日本の精神病理学を先導された。京都大学退官後は、兵庫医科大学の教授を務められた。
3代 吉田 和夫教授 (1955-1959)

村上教授の後任には、神経病理学がご専門の吉田和夫教授が京大から赴任された。しかし、名市大にいらっしゃて4年後の1959年に、享年40歳という若さで病魔に倒れられ、名市大精神医学教室の歴史においてまことに残念な結果となってしまった。
当時を知る田伏日出雄先生(1956年入局)による次のような逸話が伝わっている。「外来で印象的な事件が起こった。下を向いて黙りこくっていた分裂病の初診の患者が、突然思い切り教授のほおをひっぱたいた。患者に飛びかかろうとする私や看護婦を手で制し、教授は「気にさわることを言ったのなら御免。しかし、もし先生を叩いて気が済むんだったら、たくさんは困るけどあとひとつぐらいなら叩いてもいいよ」とのたもうたのである。気を呑まれたように患者はまた座り込み、しばらくするとぼそぼそとしゃべり始めた」
4代 岸本 鎌一教授 (1959-1969)

吉田教授の跡を継がれたのは、名古屋大学環境医学研究所長をしておられた岸本鎌一教授である。岸本教授は1932年(昭和7年)名古屋医科大学ご卒業で、ご専門は精神薄弱の遺伝生化学的研究であった。在任中、ロックフェラー財団の援助で南アルプスのふもとの隔離集落に2週間泊まり込み、名市大が精神科、名大が整形外科、信州大が血液学、順天堂大が眼科学、三島の遺伝研究所グループも参加するというスケールの大きな研究も行われた。1969年には岸本教授の構想のもと、日本では数少ない心身障害者のための総合施設である愛知県心身障害者コロニーが開設された。
岸本教授は同時に、禅に根拠をおいた森田正馬博士の体験療法に共感し「自覚的精神療法」を唱えられた。若い教室員を引き連れて曹洞宗本山永平寺に座禅を組みに行ったり、実存分析のフランクル教授*を名古屋に呼び講演会を開かれたり、国際精神療法学会で「自覚的精神療法―東洋哲学、特に仏教による」と題した講演をされた。
教室では、南山大学心理学教室の荻野恒一教授が週に1回精神病理学の抄読会を続け、精神病理学の京都学派の伝統が継承されていた。ほか、脳波(白木先生、高井先生、工藤先生、服部先生ら)、組織病理(水野先生ら)、染色体(小野先生)など活発な研究活動が行われた。
当時の入局者には、大原貢先生(のち、愛知医科大学教授)、高井作之助先生(のち、愛知教育大学教授)、山中康裕先生(のち、京都大学教育学部教授、学部長)などがいる。
*Victor Frankl。ナチスの収容所体験を元に書かれた『夜と霧』は日本語を含めた17カ国語に翻訳され、世代を超えて読み継がれている。ウィーン大学医学部教授、実存分析を唱えた。この方が名市大にいらっしゃったことがあるとは胸が熱くなる。
5代 大橋 博司教授 (1969-1973)
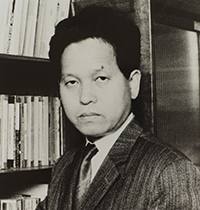
大橋 博司教授と言えば、『臨床脳病理学』がつとに有名である。今で言う神経心理学は、当時は大脳病理学と呼ばれ、大橋教授は我が国の神経心理学の先駆者のお一人である。大橋教授は掛川のご出身で、1946年(昭和21年)京都大学医学部卒業。今は名古屋市博物館となっている敷地にあった病院が、現在地の病院に移ったのが1969年、大橋教授が赴任された年であった(その病棟も2004年の新病棟移転とともになくなってしまっている)。
大橋教授は熱烈な巨人ファンで、自らも野球をされ、アンダースローの大原貢先生(1961年入局、1969年講師、のち、愛知医科大学精神科教授)と組んだバッテリーは相当のものであったらしい。
研究活動は、精神病理学(木村先生、大原先生)、脳波(吉水先生、山村先生、中西先生ら)、児童(山中先生)、精神分析(大橋一先生)などに受け継がれていった。1985年に出版された教室業績集で木村教授は「当教室は、大橋教授の時代以来、完全に臨床一筋に目を向けてまいりました。このような事情から、実験的研究を主体とする場合と比べて、業績の数はけっして多いとは申せません。しかし当教室の業績は、いずれも患者と密着した精神医療の現場からしか出てこない、実践的な色彩の濃いものばかりであることに、いささかの自負を抱いておりますし、今後もこの方向を教室の特色として継承して行きたいものと考えている次第です」と書いておられ、名市大精神医学教室の臨床研究の伝統はこの頃から築かれてきたことが分かる。
当時の入局者には、西村州衛男先生(のち、椙山女学園大学教授)、森省二先生(のち、愛知みずほ大学教授)がいる、長谷川雅雄先生(のち、南山大学教授)がいる。
6代 木村 敏教授 (1974-1986)
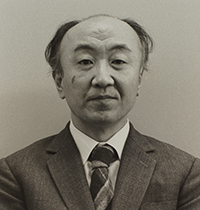
大橋教授の時、医局会の投票で助教授として指名・招聘されたのが、当時ハイデルベルクに留学中であった木村敏先生であった。1969年助教授として着任され、5年後大橋教授の跡を継いで教授に就任された。木村教授は高山のご出身で、1955年(昭和30年)京都大学医学部卒業、ミュンヘン大学神経科・精神科およびハイデルベルク大学精神科に留学。
木村教授の人間学的精神病理学を略述することは到底余人の及ぶところではないが。その精神医学の影響は、狭義の精神医学の枠を超えて哲学・思想に亘り、また日本を越えてドイツ・フランスに及んでいる。著書に『異常の構造』(講談社、1973)、『時間と自己』(中公新書、1982)、『偶然性の精神病理』(岩波書店、1994)、Ecris de psychopathologie phenomenologique(PUF, Paris 1992),Zwischen Mensch und Mensch(Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1995), L’Entre(J. Millon, Grenoble 2000)ほか。訳書に ビンスワンガー『精神分裂病』I・II(共訳、1960-61)、同『現象学的人間学』(共訳、1967)、ヴァイツゼッカー『ゲ シュタルトクライス』(共訳、1975)、ブランケンブルク『自明性の喪失』(共訳、1978)、テレンバッハ『メランコリー』(1978, 1985)、ハイデッガー『ツォリーン・ゼミナール』(共訳、1991)(以上みすず書房)ほか、がある。 1981年第3回シーボルト賞(ドイツ連邦共和国)、1985年第1回エグネール賞(スイス、エグネール財団)、2003年第15回和辻哲郎文化賞受賞。『時間と自己』などの数多くの著作は『木村敏著作集』全8巻 (弘文堂、2001)にまとめられている。
木村教授時代の前半の大きな特徴は、やはり医局会の投票で招請された中井久夫助教授の存在であった。木村教授がよく語っておられたが、当時年に1回東京大学出版界の主催で「分裂病の精神病理学」シリーズの執筆のための泊まり込みの討論会があったが、その箱根の宿の温泉の湯煙の中、難解で知られた安永浩のファントム理論をものの見事に解説してくれたのが中井先生との出会いであったそうである。お二人がいらっしゃった頃は今も「木村-中井時代」と呼ばれ、同門会員の懐かしみ、また憧れる時代である。中井先生の広く、深く、ユニークな見識も略述を拒むところであるので、当時の医局員の思い出話を掲げる「教授も助教授もたばこを吸いながら診察をする。時には、患者さんも吸う。さらにポリクリの学生まで吸う。助教授は突然患者とひそひそ話を始める。周りは沈黙し耳を傾けるが、まったく聞こえない。シュライバーは呆然とする」(早稲田直先生)「木村先生と中井先生のコンビのもとで、教室は自由で創造性にあふれた不思議なるつぼと化していた。当時は大学とはそんなものかと思っていたが、今にして見れば奇跡に近い贅沢な布陣だった」(滝川先生)
当時の入局者には、滝川一廣先生(のち、愛知教育大学、大正大学、学習院大学教授)野田隆峰先生(のち、鹿児島国際大学教授)古川壽亮(のち、名市大教授)、磯部潮(のち、東京福祉大学教授)がいる。
7代 濱中 淑彦教授 (1987-1999)
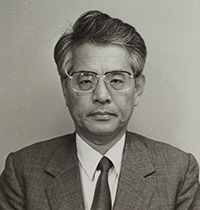
濱中淑彦教授は1999年、京都大学助教授から名市大に着任された。濱中教授は大阪のご出身で、1960年京都大学医学部をご卒業になり、1963年フライブルク大学精神神経科、1970年ベルリン自由大学神経科などの留学歴がある。
ご専門は神経心理学および精神病理学で、第5代教授の大橋教授の跡を継ぎ、名市大の神経心理学研究を近代化された。ご自身「精神科医にはいつの時代にも二つの陥穽が待ちかまえている。つまり、昔からよく言われている極端な身体論者か、心理論者か、そのいづれかに一方的に陥ってしまう危険が常につきまとっている」と述べられ、すべての精神科医が自戒しなくてはならないところである。
 濱中教授ご在任中の1996年、新しい医学研究科・医学部研究棟が完成した。研究は、神経心理(中西先生、吉田先生、仲秋先生)、思春期(清水先生)、児童(滝川先生、牧先生)、精神病理(高橋先生)、脳波(辻先生、堀先生)、エビデンス精神医療(古川)と引き継がれていった。
濱中教授ご在任中の1996年、新しい医学研究科・医学部研究棟が完成した。研究は、神経心理(中西先生、吉田先生、仲秋先生)、思春期(清水先生)、児童(滝川先生、牧先生)、精神病理(高橋先生)、脳波(辻先生、堀先生)、エビデンス精神医療(古川)と引き継がれていった。
8代 古川 壽亮教授 (1999-2010)

古川壽亮教授は、1999年に講師から教授に昇任された。古川先生は京都のご出身で、東京大学をご卒業後に名市大精神科に入局された。教授にご就任後に、さまざまな改革に乗り出され、臨床を大切にする大学精神科であるという伝統を堅持されながらも、少ない人員で世界に伍する診療、研究を、という言葉を旗頭に、御自身が専門にされていたエビデンス精神医療、認知行動療法、そして名市大の伝統としての神経心理学、新たな潮流としてのサイコオンコロジーなどを柱に据えられ、名市大精神科を力強く牽引された。精神医学のみならず、臨床疫学、統計学、そして語学(英語、フランス語のみならずドイツ語などにもご堪能であったと記憶している)といった多才に恵まれた方でありながら、謙虚で温かいお人柄に魅了され、数多くの精神科医が全国から名市大精神医学教室の門を叩いた。古川教授の御采配で、数多くの輝かしい実績が残された。例をあげると、古川教授の在任約10年の間に、病棟の入院患者数39%増、平均在院日数48%短縮、外来患者数25%増、新患数44%増、副科患者数311%増が達成され、毎年発表される名市大診療各科の評価でも常に1ケタの順位を誇るようになった。また30名を数える者が古川教授の指導で学位を授与され、2010年度大学ランキングで名市大は「精神医学、心理学」分野で論文被引用数が全国3位となった。
古川教授は2010年7月から、京都大学大学院医学研究科健康増進・行動学分野の教授として転任され、現在もご活躍中である。
なお、古川教授が在任中の2004年に現在の新病棟が、2007年に新外来棟が完成した。
教室について Contents
- 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野
- 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 Phone: 052-851-5511(代表) Fax: 052-852-0837
Copyright © Dept of Psychiatry, Nagoya City Univ Graduate School of Medical Sciences, All Rights Reserved.