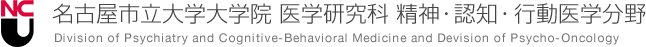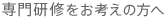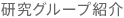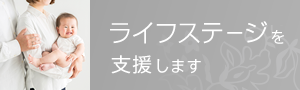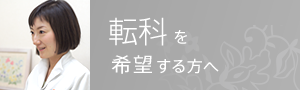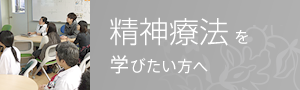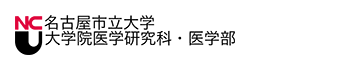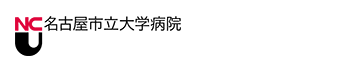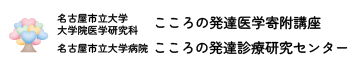HOME > 専門研修をお考えの方へ > 専門研修をお考えの方へ> 専門研修において目指すこと
2018年度からはじまる日本専門医機構が認定する専門医制度への対応も万全!
患者さんとの治療関係(治療同盟)を築く
精神科臨床の一番の基本、それは患者さんとの治療関係です。患者と医師の間に信頼関係がなければ、患者さんはそもそも症状や悩みを十分表すことができず、適切な診断・治療に至りません。精神疾患はその症状が医師-患者関係に影響するという点で、身体疾患とは大きく異なります。OSCEレベル、一般診療科に求められるレベルよりはるかに深く、共感に基づいた安定した治療同盟を築くには、専門的技量が必要です。
精神科の面接技量の習得は、外科系の手術技量の習得と似ているところがあります。座学では学ぶことができず、指導医の面接を見学し、自分の面接の指導(スーパービジョン)を繰り返し受けることが必要なのです。当教室には精神療法(認知行動療法、対人関係療法など)、コンサルテーションリエゾン、サイコオンコロジー(精神腫瘍学)、緩和医療、家族心理教育、児童精神医学、認知症、てんかん、電気けいれん療法などの臨床を専門とする指導医が多数在籍し、そのような機会が豊富にあります。また、半年ごとに指導医が交代する研修システムを採用しており、複数のエキスパートから学ぶことができます。このような手厚い体制で精神科臨床の基本を習得できる専門研修は全国をみわたしてもそんなに多くはないと自負しています。
患者さんの人生全体を考えて診療する(Formulation-based approach)
精神医療のやりがいはたくさんありますが、最も大きなやりがいは「患者さんの人生全体に関わることができる」という点ではないでしょうか。精神科では疾患だけを見ていては十分な診療ができません。患者さんの幼少期からの生育歴、生活歴、家族歴などの縦断的評価から疾患の形成過程を、現在の症状・生活・対人関係などの横断的評価から疾患の維持過程を推定し、作業仮説(フォーミュレーションや見立てと呼びます)を立てることが必要です。優れた臨床医はその仮説を患者さんとともに検証しながら協力して診療を進めていくのです。
当教室では、定例のケース・カンファレンスを通してフォーミュレーションの立て方を自分で試行錯誤しながら学び、指導医の指導のもとで日々の診療の中で実践していきます。そのような実践を継続することで、患者さんの立場から患者さんの体験を理解するようになり、患者さんの人生全体を考えながら寄り添って支援できるようになります。そうなったとき、あなたは精神科医としてのやりがいをきっと実感するでしょう。それが真の精神科専門医であり、helping professionalではないでしょうか。
エビデンスを重視して診療する(Evidence-based approach)
このように、患者さん一人一人の個別性は大切ですが、それだけでは自己流の診療になってしまう恐れがあります。精神疾患も身体疾患と同様に、各診断で疫学・症状・経過・治療反応性・予後などが一定の範囲内にあり、人類の知恵であるエビデンスを目の前の患者さんに適応することができるのです。
ますます増え続ける医療情報から真に重要なものをセレクトし、どれが真実で、どれが目の前の患者さんに適応できるかを見分ける能力はとても重要です。自己流の診療に陥らず、患者さんに世界標準の診療を提供し続けるためには必須と言えます。当教室でその能力を磨くことができます。
世界標準の症候学・診断学・治療学を学ぶ
最初から特定の病院に勤めていると、そこのローカルな診療文化しか学ぶことができません。当教室にはさまざまなバックグラウンドを持ち、世界水準の臨床・臨床研究を行っている精神科医が集まっているため、現在の日本で、そして世界で何が標準で何が共通になっているかに接することができます。また、関連病院とのネットワークによる継続的な研修で医療者としての幅が広がります。これらを通して、私たちはあたたかいこころをもった一人の人として患者さんを支える「アート」と客観的な「サイエンス」を融合させてベストな診療を提供できる精神科医になれることを医局員一同目指しています。
基本を丁寧に学び、エキスパートを目指す
名古屋市立大学病院の精神科病棟は28床と多くはないので、入院患者さんの主治医として関わることのできる症例数は若干少なく見えるかもしれません。しかし、いずれ多忙な市中病院の臨床現場は経験することになります。基本を学ばず、粗雑な診療をこなし続けていると、誤った経験ばかりが増えていくことになりかねません。
専門研修は、指導医を含むチーム制で入院患者さんの診療を担当することから始まり、徐々に外来診療へと進んでいきます。外来や当直で担当した患者さんについても、指導医による指導や相談の機会を定期的に設けています。そもそも臨床に熱意を持つ指導医が集まっていますから、いつでも相談することができます。
私たちは、患者さんの背景を深く理解することなく、薬物療法一辺倒で対処しようとする精神科医は目指していません。もちろん、特に外来診療においては、私たちも短時間に多くの患者さんを診察せざるを得ない現状がありますが、基本を学んでいれば、患者さんにかける時間は短くても、とても内容が濃い診療を提供できます。たとえば、同じ10分の診療であっても、患者さんの症状の変化に対して対症療法的に薬剤変更をするのみで終わる診療と、患者さんがドアを開けた瞬間から表情や立ち居振る舞いに注意を向け、きちんと挨拶を交わし、患者さんのがんばりにねぎらいの言葉をかけたうえで、薬物変更の目的を伝えてエビデンスに基づいた薬剤変更を行う診療では患者さんの回復状況は当然異なってきます。精神科医のキャリアの最初の時期に基本を丁寧に学ぶことは、エキスパートへの確実な礎になりますし、絶対に必要なものだと私たちは考えています。
最先端の精神科臨床・臨床研究に触れる
前述のように、当教室には精神療法(認知行動療法、対人関係療法など)、コンサルテーション・リエゾン、サイコオンコロジー(精神腫瘍学)、家族心理教育、児童精神医学、老年精神医学、精神神経薬理学、てんかん、電気けいれん療法などの臨床を専門とする指導医が多数在籍しています。目の前の患者さんにベストの医療を提供する努力は並大抵のものではありません。誇りを持ってそのような努力を続けているエキスパートに接することができます。
また、当教室では、患者さんに今より少しでも良い精神医療を提供することを目指して、日夜、臨床研究を行っています。専門技能を身に付けた先には、専門をさらに磨いて広く人々に貢献する道が開かれています。
名古屋市立大学精神科を受診する多くの患者さんから、「周りからこちらを勧められて来ました」という声をいただいています。当教室は、患者さんに信頼される医療を、誇りを持って提供し続けています。
また、当教室で専門研修を終えた医師は、他の医療施設から、その実力や人間性をとても評価いただくことが多く、大変うれしく思っています。私たちの最大の喜びです。
精神医療を志す先生方、私たちともに臨床を学びませんか。
お待ちしています!
連絡先:医局長 白石 直 ncupsychiatry@gmail.com
専門研修をお考えの方 Contents
- 名古屋市立大学大学院 医学研究科 精神・認知・行動医学分野
- 〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1番地 Phone: 052-851-5511(代表) Fax: 052-852-0837
Copyright © Dept of Psychiatry, Nagoya City Univ Graduate School of Medical Sciences, All Rights Reserved.